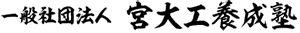
今回は、「1人工」の仕事について自分の体験を踏まえ「1人工」とは何なのか?
その分働くためにはどうしたらいいのか、解説していきます。
目次
先日、お寺の改修工事の現場にて1日作業する日がありました。壁解体と柱不陸調整の仕事でした。木部解体、土壁、古い電気配線、釘処理、生け捕り解体など。神社仏閣の解体作業は色々な作業があります。実際私は作業の中で、次はこうした順番で解体したらいいかな、木の表面を傷つけないようにするにはどうするべきかなと、考えながらしていました。しかし、作業がはかどらず、時間ばかりが過ぎていきます。半日を終えて振り返ってみると全然進んでいません。
✅必要な工具が腰袋に入っていない→その都度誰かに借りたり、探している
✅どこまで解体するのか不明確→最終仕上がりを把握できていない。
✅解体工具が適切なものを選べていない→どのように攻めるべきか事前検討できていない
結果、1人工分働いたとはとても言えない結果に終わってしまいました

簡潔に言うと、「一人工」とは職人1人が1日でこなさなくてはいけない仕事のノルマです。加工場での作業の場合、流れとしては木造り→墨付け→刻み→仕上げ→組み立て、となります。大きな建物で長丁場の場合は、木造りここまで終わらせよう。刻みは部材単位で終わらせよう。など、その日ごとに決まっています。また小規模の場合は、1日で完成まで終わらせようと目標が設定されています。
現場棟梁が全体の流れを決め、そこに向かって1人1人がノルマをこなしていきます。

宮大工の仕事は、木を加工したり、組み立てたりだけではありません。
建物を解体する日。解体した土のう袋を運搬する日。遠くの現場へ移動し、生活の準備をする日。また、そのための積み込みをする日。など様々な仕事があります。
では、これら多くの仕事それぞれの1日の価値は違うのでしょうか?
答えは、全て同じ「一人工」です。
解体の日にはそのノルマが当然あり、移動日もまた同じです。職人が1日仕事をするというのはそういう意味になります。

まず、仕事をするのに「待ち」の姿勢でいてはいけません。これまで私は、会社に所属しているから仕事が用意されていて、そこから仕事をもらうのが当然のように思ってきていました。本来、仕事をするためには、営業・設計・積算・契約・工事管理をしてくれる人がいるおかげで私は大工仕事に集中してする事が出来ますが、それが当たり前のように錯覚していました。そう考えた時に、「1人の大工」として最大限できることは何か?次の仕事を常に予測・準備して、仕事を自分から積極的に仕事を取りに行くことだと私は思います。
「待ち」の姿勢でいることは、結果が何もついてきません。自分でやりきることを考えている人と、誰かの答えを待っている人では、いざ1人で何かする時に大きな差が生まれます。社会に出たら、誰も正解を教えてくれません。
実際の私の経験として「待ち」の姿勢はよくないで、どんどん行動を起こしましょう。人は行動によってしか評価されない。自分から行動することが成長への第一歩です。
仕事をするうえで段取り八分という言葉があります。当日の仕事の出来は前日の段取りで8割決まるという意味です。
✅明日の仕事は何か?
✅誰と一緒に作業をするか?
✅必要な道具は何か?
✅作業手順はどうするか?
事前に明確なものにすることが段取りを組むということです。あとは作業するだけなので現場での誤差をリカバリーするだけで一人工分の仕事ができる
仕事をする時は基本1人ですが、同じ現場内には他の人が同じように1日作業をしています。2人で1つのものを納める日も当然あります。なので、自分のことを考えればそれでいいわけではありません。現場棟梁を筆頭に上の立場に立つ人は現場の1日の仕事の積み重ねが工事完成には不可欠です。その人にとっては、現場全体をまとめ、職人、見習いみんなのことを考えることも「一人工」の仕事です。
会社から給料をもらう。日当分のお金をもらう。というのは当人が「一人工」分働いて、初めてもらえるものです。「一人工」分働いていないというのはその分だけその工事の中でマイナスです。1人の職人として、「一人工」仕事をこなすことを当たり前にできるように行動していきましょう。
全国5校舎にて宮大工体験を受け付けています。岡山西大寺校では、講師の田中が大工道具の解説、実践を行います。校舎長の坪井住職より、今の自分のためになる貴重な法話を聞ける機会もございます。是非、体験に参加してみてください。


田中 尚哉 23歳(2001年生まれ)
岡山西大寺校 講師 6年目
長野県出身で、高校卒業後、宮大工養成塾に入塾(5期生)し3年間の住込み修行を経た上で卒塾。静岡県の宮大工企業に宮大工ドラフトで1位指名を受けて2年間従事。そんな時、岡山西大寺校の開校を知り、宮大工養成塾岡山西大寺校の講師に志願。将来独立願望があり、現在は西大寺の棟梁になるための修行を行いながら、塾生の模範となるように日々研鑽しています。
趣味:コーヒー